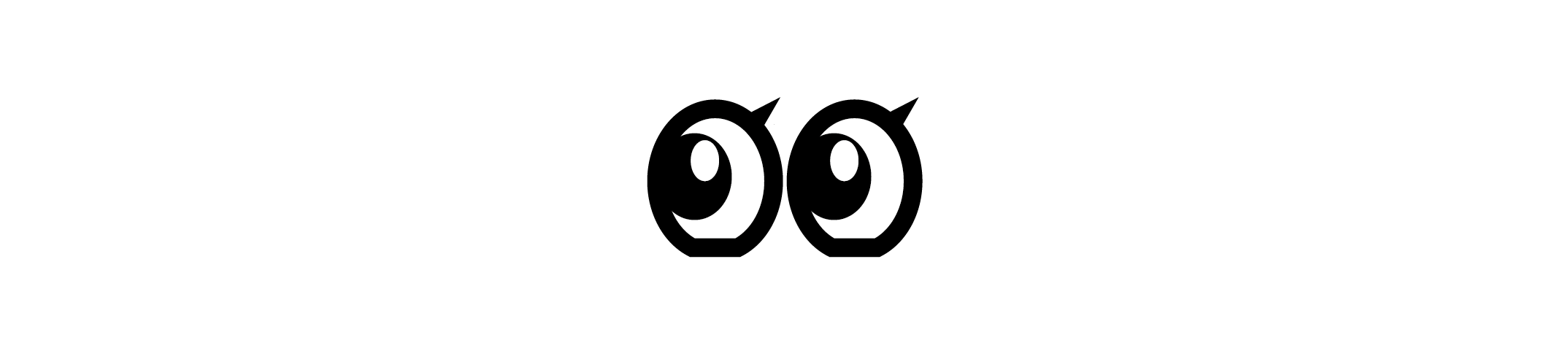厚生労働省がん対策推進企業アクションは10月24日(水)、メディアセミナー「乳がん検診最前線-乳がんは唯一、自分で見つけられるがんです-」を東京大学病院(東京都文京区)で開催した。
はじめに、セミナーの司会・コーディネーター西田沙緒里氏(ライフサカス代表)から挨拶があり、そのなかで自身も乳がんの経験者であることを告白した。続いて、大石健司氏(がん対策推進企業アクション事務局事務局長)から、がん対策推進推進企業アクションについて、がん対策を企業単位で推進する運動であり、推進企業アクションパートナー企業は、2705社・団体、推進パートナー従業員総数にして約7,045,564人にのぼる事業であること、そして、10月はピンクリボン月間であることから、乳がんへの関心を高める運動に力を入れていることが紹介された。
講演では、中川恵一氏(東京大学医学部放射線科准教授)をはじめ、乳がん経験者である、元SKE48メンバーの矢方美紀氏と風間沙織氏(一般公募)が登壇し、それぞれの講演をもとに議論を交わした。
はじめに、中川氏から、乳がんについての説明がなされ、また、日本人のヘルスリテラシーの低さと、がん教育の必要性が訴えられた。がんの生涯罹患率全体としては男性62%女性47%と男性の方が高いが、若年層に関しては女性の方が罹患率は高く、その多くが乳がんである。その主な要因が女性ホルモンであり、現代では、栄養状態の向上により初潮が早く閉経が遅くなっていることに加えて女性が妊娠する回数が減っているため、生涯月経回数が大幅に増加、女性ホルモンの影響を強く受けやすくなっている。また氏は、日本人の健康への理解が著しく遅れているという問題に言及し、昨年4月から全国の小・中・高等学校でがん教育が開始されたことを踏まえて、今後は大人のがん教育こそ取り組まれるべき課題であり、企業ががん教育を担うことを提言した。がん対策の要は生活習慣の改善による予防と早期発見の二段構えであり、特に乳がんは唯一の自分で触れるがんであり、早期発見のためにマンモグラフィ、超音波検査に加えて、月に一度の自己触診が重要となることが訴えられた。
次に、実際に乳がんを経験した2人から、自身の乳がんについて、自己触診による発見から現在に至るまでの治療の経緯を、発見、診断、手術といった場面で感じたことを織り交ぜながらの講演がなされた。
矢方氏は、自己触診により乳がんを発見出来たことは偶然だったとしながらも、アイドルの頃からグラビア撮影のためにバストアップのマッサージを日常的に行うなど、自分の体のケアに関心を持っていたことが、胸にしこりを発見した要因であったと話した。がんというと痛いというイメージがあったことから、しばらくすればしこりはなくなるものではないかと、病院に行くことをためらっていたものの、年上の知人に受診を強く勧められ診断に至った。手術に際して最初は温存も考えたが、「自分の人生を楽しみたいし、やりたいこともある」と確実さを優先し全摘出を選んだこと、手術同時再建も視野に入れていたが、術後の予防的放射線治療への影響を考慮し控え、今は再建の予定はないことを話した。「明日何かあっても、今日を悔いなく過ごせれば」と前向きな姿勢で、がん治療とともにタレント業を継続し、活動のなかで乳がんの啓発を行っている。
風間氏は、妹が乳がんの診断を受け、母も乳がんであったことから、自身も乳がんである可能性を疑い、自己触診してみたところしこりを発見した。居ても立っても居られず、その晩のうちに、ネットで病院を予約したという。氏は、毎年マンモグラフィによる乳がん検診を受けており、半年前にも検診を受けているのにも関わらず発見できなかった原因として、高濃度乳房を挙げた。自身のマンモグラフィと超音波検査の画像を比較し、マンモグラフィでは確認できず、一方の超音波検査では、はっきりと確認できることを示し、二つの検診では各々見えるものが異なるため双方を併せて受診することを推奨した。手術の前年に保険適用になったことから、全摘出とともにインプラントによる再建をし、後に乳頭と乳輪も再建。「遠目には見ても分からないくらいであり、とても満足している」とのことだった。また、がんと仕事との両立についても啓発を促した。
講演の後にディスカッションと質疑応答がなされ、中川氏はがんが1㎝から2㎝の早期に発見・治療できるかが全てを決めるとし、また早期であれば5年生存率が高く、かつてのような死病ではないことを強調し、一方で、身体に影響を及ぼさない程度の微小ながん細胞は殆どの人が持っているとしつつ、甲状腺がんの死亡率が1%程度で横ばいになっているデータを提示。こうした死亡率の低いがんまで徹底的に治療しようとすると、結果的に身体への影響は、マイナスになってしまうという過剰診断の問題も喚起した。